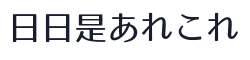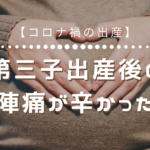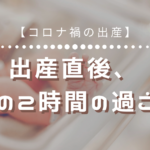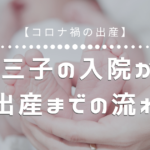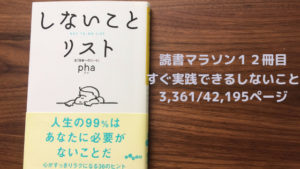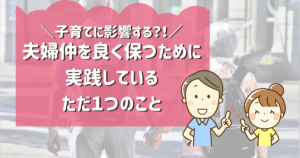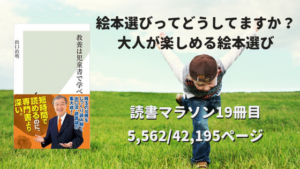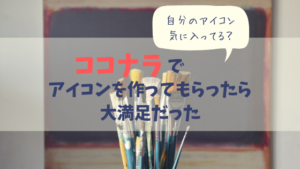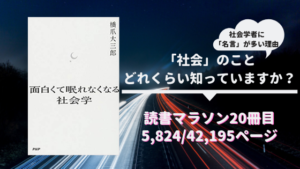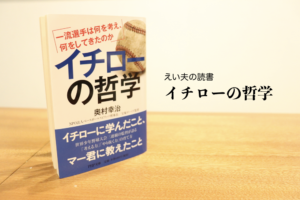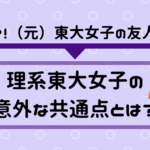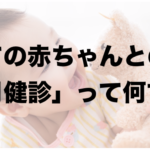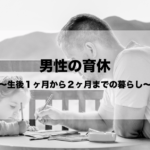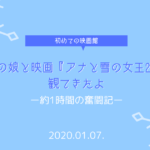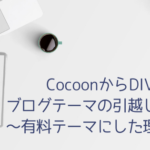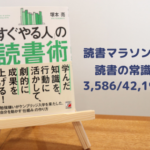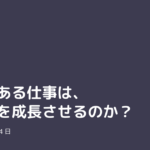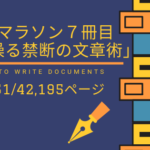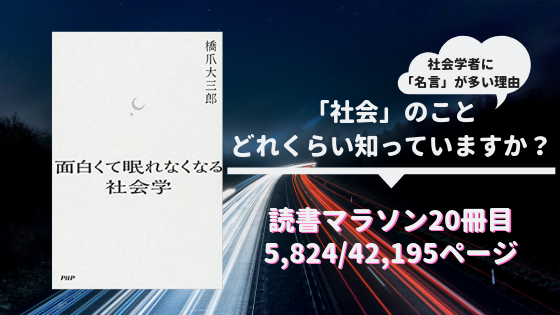
アドラーやドラッカー、マックス・ウェーバーは名言を数多く残しているの有名です。
名前を聞いたり、見たりしたことがある人は多いのではないでしょうか。

![]()
『社会学者』って言って、社会のあらゆることを研究していた人なのよ!

![]()
それでちょっと「社会学」っていうのに興味が湧いたんだそれと、
会社もネットもいわば「社会」だから、
「社会学」って勉強してみたら、仕事とかに役に立つんじゃないかなって思って読んでみたの!

![]()
意外と知らないことが多いんだってことがわかったのよ!役立つかどうかはわからないけど、世の中に対して少しだけ興味が持てるようになったよ!
あと、「名言」が生まれるのは「人」が構成している「社会」とずっと向き合っていることで、「真理」みたいなのが見えてくるからなんじゃないかなって思ったよ

えいこちゃんが「意外と知らなかった」こと、ボクにも教えてよ!
![]()
順番に見てみよう!!
- 「言葉」に興味がある
- 「税金」を取られるのは理不尽だと思っている
- 「共産主義」と「社会主義」の違いがイマイチよくわからない
- 「自由」に生きたい
もくじ
「面白くて眠れなくなる社会学」ってどんな本?
面白くて眠れなくなる社会学
橋爪大三郎 PHP研究所 (262ページ)
著者 橋爪大三郎さんってどんな人?
1948年、神奈川県生まれ。社会学者。
東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。
執筆活動を経て、1995-2013年、東京工業大学教授。現在は名誉教授。
言語を社会現象の根幹に位置づける言語派社会学の構想を展開する。
『言語ゲームと社会理論』『仏教の言説戦略』(勁草書房)、『はじめての構造主義』『はじめての言語ゲーム』『ふしぎなキリスト教』(共著)『おどろきの中国』(共著)(講談社現代新書)、『世界がわかる宗教社会学入門』(ちくま文庫)、『橋爪大三郎の社会学講義』(ちくま学芸文庫)、『世界は宗教で動いている』(光文社新書)、『社会の不思議』(朝日出版)など、著書が多数ある。
どんなことが書いてあるの?
この本は、中高生向けに「社会学」をわかりやすく解説するために書かれた本です。

![]()
この本には、こう書いてあります。
小学校の社会科は、社会学ではありません。中学、高校の公民や倫理社会も、社会学ではありません。大学で学ぶのが、社会学です。
(中略)
社会学は、社会科学のひとつです。大きく言えば、科学(サイエンス)です。
(中略)
社会科学は、社会から法則を取り出して、解明します。需要供給の法則とか、有効需要の原理とか。
社会には、法則があります(知ってましたか?)。主観的願望にもとづいて、こうなってほしいとみんなが思っても、社会はその通りに動いてくれません。だから、社会科学が必要なんです。
そんな社会科学のなかで、社会学はちょっと特別です。
(中略)
人間が社会をいきていくとき誰もがぶつかる問題を、社会学は残らず正面から受け止めるということです。そうすると、あまりきれいに法則を取り出せません。そのかわりに、社会を生きる人間の真実のすがたの、いちばん深いところまで考えることができます。「面白くて眠れなくなる社会学」橋爪大三郎

”社会を生きる人間の真実のすがたの、いちばん深いところ”まで考えるから、人間のことをよく理解して「名言」となるような文句が出てくるんだねー
ボクも少し興味が湧いてきたよ
![]()

- 言語:言語を使う。言語をしゃべる。これは、人間だけの能力です。
戦争:戦争とは、《暴力を用いて、自分の意思を相手に押し付けること》、をいいます。
憲法:憲法は手紙です。人民から、国にあてた手紙。その国の政府職員に向けて、こうしなさいと約束させるものです。
貨幣:貨幣は、大昔からあったわけではありません。
資本主義:資本主義とは、資本が、特別なはたらき方をする経済のことですね。
私有財産:私有財産は、私たちの社会の基礎です。ところが、この私有財産の制度は、そんなに昔からあったわけではありません。 - 性:性とは、体と体の関係、のことです。人間は生きていますが、それは、人間の体が生きているのです。
家族:家族があるのは、人類(ヒト)の特徴です。
結婚:結婚は、世界中、どんな民族や文化にも認められる習慣です。
正義:正義とは、なんでしょうか。正義とは、正しさが外からやってきた、という感覚えす。
自由:自由とは、人間が、思ったように行動したり、好きなように考えたりできること、をいいます。これは、人間の生まれついての性質です。 - 死:人間は生き物ですから、死にます。動物や植物も、生き物ですから、死にます。死ぬのは生き物の宿命ですね。
宗教:宗教は、人類の文化になくてはならないもの。いや、人類の文化の中心です。
職業:職業とは、仕事のことです。収入があって、かなりの時間をさいていて、それで生活を支えている、そういう活動をいいます。
奴隷制とカースト制:インドに、カースト制という制度があります。インドにしかない、特別な社会の仕組みです。
幸福:幸福とは、人間が人間として生きていることが、充実している状態ですね。生きる目的と言ってもいい。

![]()
中高生向けに書かれているから、文章は優しくて意外とスラスラ読めるのよ!
今回は全部を紹介するのは無理なので、
私が「知らなかった!」「知っててソンはない!」と思った3つをご紹介します。
(紹介するポイントは文字を大きくして色を変えています)
「言語」を操れるのは人間だけ
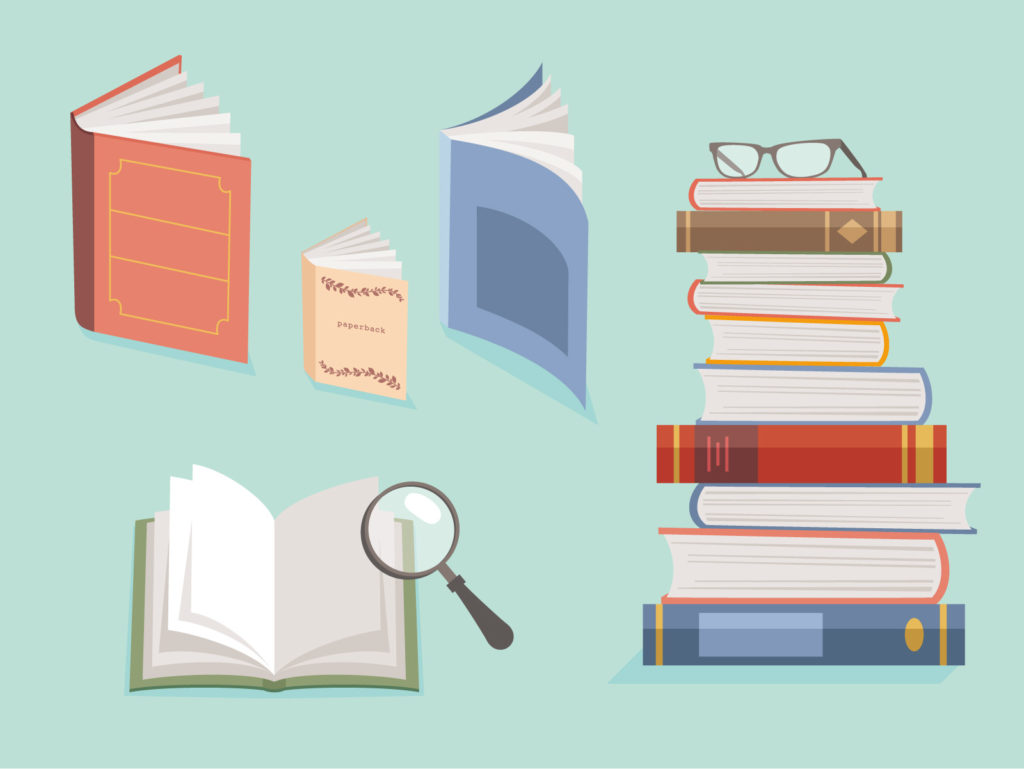
世界はモノに名前をつけることから始まる
言語の意味は、この世の中の出来事やありさまと、関係しています。言語があることによって、この世界は豊かになり、広がりをもち、人びとが共有できる空間になるという性質があります。
「面白くて眠れなくなる社会学」橋爪大三郎
![]()
その根本には、「言葉がモノを指し示すことができる」という性質があります。
モノにはそれぞれ名前があるんです。
これを名詞と私たちは呼んでいます。
世界は名詞の集積になって、名詞によって指されるモノの全体になって。つまり、意味のある空間になります。
「面白くて眠れなくなる社会学」橋爪大三郎
「世界は名詞の集積」ってあまり考えたことがなかったのです。
確かに何か人に説明したい時に、モノに名前が付いていないと説明できないですよね。
例えば、
![]()
1つの「携帯電話」という言葉を説明するだけで、これだけの名詞が必要です。
それぞれの名詞を説明するためにまた、他の名詞が必要なのです。
名詞にについてはまだ解明されていないことも多いそうで、その世界は奥が深いみたいです。
普段何気なく使っている「名詞」ですが、本気で研究している人もいるんだと思うと少し面白いですね。
言葉は知識を共有するツール
言葉を使った知識の共有に、「伝聞」という現象があります。
「伝聞」というと古典で出てくるイメージですが、実際はどんな感じかというと...

◯◯ちゃんのお母さんって看護師さんなんだって!
![]()
えいこさんは、◯◯ちゃんのお母さんは知っていますが、看護師さんだということは知りませんでした。
ホッグくんが教えてくれたことで、ホッグくんの知識がえいこさんの知識にもなりました。
伝聞とは要するに、人に聞いたので知っているということ
伝聞によって、ほかの人の経験や知識を自分の経験や知識に接続できます。
逆に自分の知識や経験を、べつの誰かの経験や知識に接続することができるのです。
こうやって人々が知識や経験を伝聞によって広げていくことで、社会がどんどん豊かになっていきます。
でも、「伝聞」には問題点があります。それは「伝言ゲーム」をするとわかるのですが...
広がっていくことで、内容がどんどんあやふやになって言ってしまうことです。
内容が拡散しないように伝える技術としては、ことわざとか、言い伝えとか、物語とかのかたちに変換することが挙げられます。
「言葉」によって、自分が持っていない知識や経験がいくつも共有されているのです。
文字の威力
知識を共有するために、「言葉」を文字で書きます。
文字というのは、すばらしい工夫で、言葉を写し取るモノというか、記号なんですね。言葉は、文字に写し取られた時点で、固定したモノになって、もはや変化しなくなります。
「面白くて眠れなくなる社会学」橋爪大三郎

固定化することで、
![]()
私たちは1000年前に書かれた、源氏物語を読むことができるよね?

![]()
日本人のほとんどが同じように知ってる!
それは、紫式部が1000年前に「文字」で源氏物語の「言葉」を固定化していたからなのよ!

「時代を超えて読まれる」ってことだね
![]()
「言葉を固定化」することでできることがもう一つあるのよ!

![]()
源氏物語は英語に翻訳されて世界中の人も読むことができるのよ!

文字の威力ってスゴイ!!
文字は最初は、税金を集めるために政府が使ったものだとされています。
他にも、契約を書きとめたりすることもできて、広い社会を治めるのにはとても役立ちます。
でも、「文字」はどんな知識でも書きとめられるし、社会を生きるための知恵が凝縮されています。
私たちは小さい頃から「文字」習って、本を読み、生きるのに必要な知恵を手に入れます。
「言語」をうまく使いこなして、この社会を豊かに生きるのは、誰でもすぐできることなのです。
- 言語を使えるのは人間だけ
- 言語は情報や知恵、知識を共有するツール
- 「言葉」を「文字」に固定することで、情報が正確に伝わり社会が豊かになる
私たちの社会の基礎?!「私有財産」とは

私有財産は、近代社会特有の新しい考え方だそうです。
では、私有財産とはいったいなんでしょう?
- モノは必ず誰かのもの(誰かが所有している)
- 特に不動産は大切なものだから、所有者の名前を届け出る
- 動産でも車のように大切なものも、所有者を明らかにしておく
- それ以外のものは届出はないが、誰のものかは決まっている
これを、所有者ではない誰かが勝手に使ったり、奪ったりしてはいけません!たとえ政府であったとしても。
「政府」は、私有財産を守るために設立した団体で、人々の利益を守らなければなりません。
政府は本当に私有財産に手をつけないの?
そんなことはありません。むしろ、私有財産を侵害しながら、活動します。

人の財産を奪って活動するってどう言うこと????
政府の活動資金は「税金」でまかなわれます。
「税金」はそれぞれが持っているモノを無理やり取り上げるので、私有財産の侵害です。

これって完全にアウトじゃない?!
僕たちの、財産を政府が搾り取ってるってことでしょ?
![]()
でも政府は、お金がないと活動できないのよ!
税金を取らないことにすると、活動ができない、つまり無政府状態になっちゃうの。
自分の財産はどうやって守る?

そしたら、自分で自分を守るために武装したりしなきゃいけなくなっちゃうね。
私有財産制は金持ちがますます金持ちになる仕組み?
「財産」とは、労働の成果です。
でも相続すれば働かないでお金が入ってくるし、利子や地代は不労所得だから正当な収入ではない。
相続する金額が大きかったり、前の世代が所有していたモノで資産が雪だるまのように膨れ上がって、お金持ちはますますお金持ちになる格差が拡大します。
これが社会の、矛盾と階級対立の原因だ!!とマルクス主義は主張しています。

![]()
これが共産主義と言うの。
- 平等第一!
- 私有財産制度は完全に撤廃しよう!
- 全てのモノは、国有か集団所有になる
- 国民の財産(資本)は役人が管理する
→国民の自由が奪われてしまう、役人の権力が大きくなりすぎる
共産主義と似たような考え方に「社会主義」があります。
- 不平等はなるべくない方が良いんじゃない?
- 私有財産は認めようよ
- 政府はお金持ちから少し多めに税金をとって、恵まれない人のために使おう
社会主義を掲げる政党は「社会党」、共産主義を掲げる政党は「共産党」と名乗るのが一般的です。
![]()
これから、これを意識して各政党の主張を聞いてみようと思います。
「リバタリアニズム」
- 政府が私有財産に手をつけるのは犯罪だ
- でも、最低限の公共サービスは認めるよ(警察とか、消防とか、救急医療とか)
このサービスのためにお金を取るのはしょうがない - それ以外の、水道、交通、刑務所、郵便などは全て民営化してしまえ!
→「小さな政府」の主張
この反対が「リベラリズム」です。
- 税金はたくさんとっていいよ
- 政府が責任を持って公共サービスや福祉をやってね
- 税金はたくさん払ってるんだから言いたいことは言わせてもらいます
→「大きな政府」の主張
日本はちょうど中間にいます。どんな政府にしていくかは私たち日本国民の判断に委ねられています。
- 私有財産という考え方は最近出てきた
- 政府は私有財産から「税」を取らないと活動できない
- 格差を少なくするために、私有財産をどれくらい政府が使って良いかで政治的な考え方が変わる
「社会主義」「共産主義」「リバタリアニズム」「リベラリズム」など
自由とはなんだ?!
社会学で「自由とは」、「人間が思ったように行動したり、好きなように考えたりできること」を言います。
人間にできて、動物にできないのは「自由に、好きなように考える」ことです。
考えることの本質は、目の前のことがらに左右されないことです。
目の前のことがらに左右されないとは、目の前にあるのとは別の状態について頭の中にイメージをつくり、その分だけ行動の幅を広げることができる、ということです。「面白くて眠れなくなる社会学」橋爪大三郎
みんなが自由に生きるとどうなる?
では、「人間が思ったように」自由に生活しようとするとどうなるかシミュレーションしてみましょう。
例えば、誰かがリンゴを持っていたとする


とっちゃおうかなー...

お友達からリンゴを取ったり、レストランで食い逃げしたり...
でもそう言うことが全部できるのが「自由」なのでしょうか?
自分ができると言うことは、相手も同じように「できる」ことがたくさんあるということです。
自分の自由を無制限に主張すると、相手も自分の自由を無制限に主張します。
結果的に、自分の自由は、とても小さい範囲に狭められてしまいます。「面白くて眠れなくなる社会学」橋爪大三郎
自分の自由を主張しすぎると、かえって自分の自由がなくなってしまいます。
それぞれの自由を確保するための社会のしくみ
そうならないために、人と人の自由の間に線を引きます。

この線は目で見えませんが、社会の中にあります。
それぞれの人の自由の範囲を決めているのが「法律」です。
ほかの人から認められた(法律で定められた)自由の範囲を「権利」と言います。
「自由について」の概念を学ぶのは、2〜3歳くらいです。
具体的には、「人のものを取ってはいけません」「自分のものはいいですよ」ということを学びます。
「言論の自由」ってなに?
世の中や社会全体について、もっとこうなって欲しいみたいなことを考えた時に
「みなさん!聞いてください!こうなった方がいいとおもうんですけど!」
といつでも自由に言っても良いというのが、発言の自由です。
発言の自由があると同時に、考えることの自由が確保されています。
こうやって考えたことを、文字に書いたり、演説したりしてみんなに伝えて良い自由のことを「言論の自由」と言います。
「言論の自由は」多くの社会でなかなか成立しませんでした。
近代になるにつれて、「法律」を作って人々の「自由を確保できる」ようになって「言論の自由が保証」されるようになりました。

自由を保証するものなんだ!!
法律を作る場は「議会」です。議会では特に、言論の自由が保証されています。
議会以外にも、新聞、雑誌、テレビでも言論の自由が保証されてているので、いろんな人が「いい考えだ」ということを書いたり発表したりできます。
「言論の自由」は、私たちの「自由」を保証する一番根本の自由なのです。
- 「自由」とはほかの人が認めた「していいこと」ができること
- 自分の自由を主張しすぎると、かえって自分の自由がなくなる
- それぞれの自由の範囲(権利)を決めている規則を「法律」という
- 「言論の自由」は私たちの「自由の根本」の自由
社会学は奥深い!
今回ご紹介したのは、「眠れないほど面白い社会学」に書かれているほんの一部です。
![]()
特に、「私有財産」の考え方で政治的な考えが変わるというのは衝撃を受けました。
ほかにも自由を守るために「法律」があること。
自由とは、自分勝手に好きなことをやることじゃなくて、ほかの人が認めてくれている「していいこと」ができることだということ。
中高生の時にこの本に出会っていれば、人生の歩み方、生ることへの考え方が変わったのではないかと思っています。
最後に、社会者ピーター・ドラッカーの名言を一つ
我々が行動可能なのは現在であり、また未来のみである。
![]()